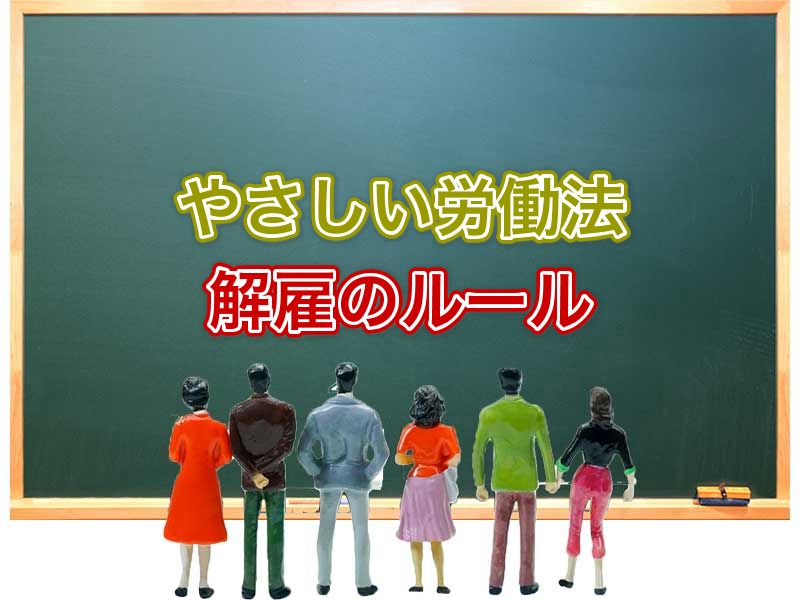解雇とは?
解雇とは、一般的に使用者から一方的に労働契約を解除することをいいます。
解雇は労働者にとっては生活の糧を失う重大な問題となりますので、労働基準法では解雇に関するルールが定められており、労働者の保護を図っています。
使用者が気を付けなければならない点は、就業規則に解雇事由を記載しておく必要があります(第89条)。

解雇には満たすべき要件があるので慎重に
解雇の種類
普通解雇
従業員との労働契約を継続するのが難しい事情がある場合「普通解雇」となる。
例えば、勤務内容が非常に悪く指導しても改善の見込みがない、仕事とは無関係な健康上の理由で長期間職場に復帰できそうにない、著しく協調性に欠けているため仕事に支障が生じ、改善の見込みがない場合など。
整理解雇
会社の経営悪化により人員整理を行うための解雇を「整理解雇」という。実施には労働組合や従業員が納得できるよう協議 、説明に努め 、次の要件を満たすことが必要 。
1 人員削減を行う明確な必要性があること
2 できる限り解雇を避けるよう努力したこと
3 解雇の対象者を決める基準が客観的・合理的であること
4 従業員または労働組合に対しその内容について十分に説明して話し合うこと
懲戒解雇
従業員が悪質な規律違反などを行ったときに行う解雇を「懲戒解雇」という。従業員に課せられる最も重い処遇のため、就業規則等や労働契約書に要件を明らかにしておくことが必要。
退職勧奨について
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。
労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりません。しかし使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。
なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。
解雇制限
解雇することができない期間(解雇制限期間)
使用者は、労働者が仕事によるケガや病気で、療養のため会社を休む期間と、治って出勤してから30日間は解雇してはなりません。
また女性の場合、産前・産後休業をする期間とその後出勤してからの30日間は、解雇してはなりません。
他の法律でも解雇が禁止されています。
(労働組合法)
・労働組合の組合員であること等を理由とする解雇
(男女雇用機会均等法)
・労働者の性別を理由とする解雇
・ 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことを理由
(育児・介護休業法)
・労働者が育児・介護休業等を申し出たこと、または育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇
解雇制限期間中でも解雇することができる場合
打切補償を支払う場合:
仕事によるケガや病気で療養を開始してから3年経っても治らない場合に、日当の1,200日分を支払うことで、療養中でも解雇することができます。
地震などの天災によって事業が継続できない場合:
地震などの天災のため、経営の継続が不可能となり廃業するような場合、療養中でも、産前・産後期間中でも行政官庁の認定を受ければ解雇することができます。
解雇の予告
使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(第 20条)。
つまり30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば、即日解雇することができます。また解雇予告と解雇予告手当の併用も可能です(第 20条)。
労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労 働者に証明書を交付しなければなりません(第 22 条)。
解雇予告などが除外される場合
次のような場合には、解雇予告をせず、または解雇予告手当を支払わなくても労働者を解雇することができます。
①天災事変その他やむお得ない事由で事業の継続が不可となり廃業するような場合
②労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき
※①②とも所轄の労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。
解雇予告が不要な人
臨時的に短期間働く労働者については、解雇予告の規定は適用されず、解雇予告などを行わずに解雇することができます。
①日々雇い入れられるとき
②2か月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に契約期間が4か月以内で使用される者
④試の使用期間中の者
※ただし、①は1か月、②③は契約期間、④は14日を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。