法律の基礎知識のおさらい
社会保険労務士(社労士)は、人事・労務管理・社会保険のスペシャリストでなければなりません。そのためには労働関係の法律の知識、あるいは社会保険の法律の知識が幅広く求められます。
社労士が必要とする、労働法、社会保険法の説明の前に、法律の基礎知識をおさらいしておきましょう。
法の体型を理解しましょう
法(法規又は広い意味での法律)は、大きく「憲法」「法律」「命令」および「条例」から構成されており、効力の優先順は、憲法 > 法律 > 命令 > 条例、で憲法が一番優先される法です。
それではまず「憲法」について、「憲法」とは国の統治組織や国民の基本的人権をなどを定める国の基本法です。憲法は法体系の中では最高法規に位置しており、法律などそれより下位の法は憲法の内容に適合する必要があります。
日本国憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない
次は「法律」です。法律とは国会の衆参両議院の議決を経て制定される法です。国の唯一の立法機関(憲法第41条)である国会によって制定される法であり、憲法に次ぐ効力があります。
「命令」は国会の議決を経ずに、行政機関が定める法です。このうち内閣が法律を施行するために定めるものは「政令」で、各大臣が法律や政令を施行するために定めるものを「省令」といいます。
例えば、「健康保険法」は法律ですが、「健康保険法施行令」は政令で「健康保険法施行規則」が省令です。政令や省令は、法律に規定されていない、より詳細な内容を規定したものになります。
「条例」は地方公共団体(都道府県や市町村区)が、自主的な立法権に基づいて、法律の範囲内で制定する法で、その地域の中だけで適用されるものです。
一般法と特例法の違いは?
「一般法」、「特例法」の言葉を耳にしたことがあると思います。「一般法」はその法が適用される領域が特に限定されていない法です。一方「特例法」は適用される領域が限定されている法のことです。
一般法と特例法に、同じ事項について、異なる規定がある場合は、基本法には特例法の規定が優先します。
労働法とは?
労働法という呼び方がされることがありますが、「労働法」という名称の法律があるわけではありません。労働者と使用者の間に生じる様々な労働問題に関係する各種法律をまとめて「労働法」と呼んでいます。
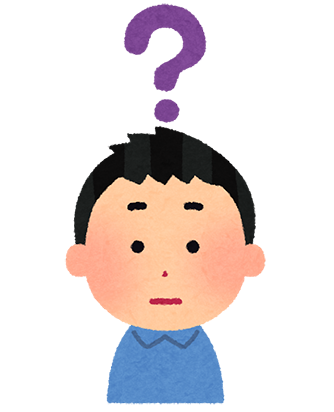
「労働法」という法律があるのですか?

労働法は、労働関係の法律をとりまとめた呼称です
実際の法律としては、労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、労働組合法などさまざまな法律があります。
労働法は、労働者自身の権利を守ることだけでなく、使用者も法律を遵守することで、労働者の働く環境を良好なものに整えることができます。そして労働者のモチベーションを向上させ生産性が向上した結果、企業の業績向上やイメージアップにつながります。
社会保険法とは?
社会保険法も、いくつかの法律をひとまとめにして呼んでいる呼称です。実際の法律としては、医療保険法として、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、共済組合に係る共済各法があります。
また年金保険法として、厚生年金保険法、国民年金法があり、さらに介護保険法があります。
これらは社会補償制度として、国民の生活を保障する制度で、社会保険(前掲の医療保険、年金保険、介護保険)、公的扶助(生活保護法)、公衆衛生(感染症対策)、社会福祉(児童福祉、母子家庭の福祉)の4分野に別れています。
社会保険法は、その1分野に位置し、日常生活の中では身近で大切なものといえるでしょう。


